|
English |
|
2018年以前のフォーラムです。
< 最新のフォーラムはこちら
モチベーション研究所第12回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「移行期の家族を支えるー離婚・再婚を経験する家族への支援」
講 師:小田切 紀子氏 (東京国際大学人間社会学部教授)
日 時:2018年10月6日(土)15時~17時(受付14時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール(公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
日本では結婚するカップルのおよそ3分の1が離婚し, 再婚するカップルのおよそ4分の1は, 夫婦のどちらか, あるいは夫婦ともに再婚である。また離婚するカップルの約60%に未成年の子どもがいるが, 日本は離婚後, 単独親権のため母親が親権者となり子どもと暮らすケースが圧倒的に多い。離婚後の単独親権制度を導入しているのは, 先進国では日本だけであり, この単独親権と日本特有の家族観が, 親の離婚・再婚後の子どもと別居親との面会交流の実施率の低さと, 母子家庭の貧困問題の一因となっている。講演では, 日本の家族観を概観し, 離婚・再婚という移行期の家族を支えるために必要なことについて子どもの視点からお話ししたい。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第12回フォーラム参加希望」として10月3日(水)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 三浦 (TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp

モチベーション研究所第11回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「well-beingを目指す心理学と大学」
講 師:大坊 郁夫氏 (東京未来大学 学長)
日 時:2018年 3月14日(水)15時30分~17時 (受付15時00分~)
場 所:東京未来大学B棟421教室(公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
対人関係は, コミュニケーションを介してのみ形成され, 推移する。その関係は運用するスキルがあってこそ展開する。しかしながら, 現実には期待するほどの円滑な関係が担われているとは言い難い。それは, どのような関係を築くのか, そのためにはどのようなスキルを磨き, 発揮すべきかの点検が十分ではないことによるのではなかろうか。
これまで行ってきた対人コミュニケーション, 社会的スキルの研究の一端にふれながら, 円滑な対人関係を築き, 維持するためのモチベーションとは, そして, そのために大学で何ができるのかについてお話をしたい。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第11回フォーラム参加希望」として3月12日(月)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 萩元 (TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp

モチベーション研究所第10回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「災害リスクを考える:正しく怖がり, 正しく行動をとるために出来ること」
講 師:申紅仙(しんほんそん)氏 (常磐大学 人間科学部心理学科 教授)
日 時:2017年 12月2日(土)15時~17時 (受付14時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール (公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
災害時, 私たちは状況を正しく判断し適切なタイミングで避難することで, 自分と家族の身を守ることが出来ます。しかし,残念ながら私たち人間は, 目の前で起こっている問題を正しく判断することが苦手なようです。たとえば, 東日本大震災では, 住民の避難開始が遅れてしまったり, 制限されていた乗用車を使用してしまったりしたことで被害が大きくなってしまいました。
本講演では, 様々なケースを紹介し, 災害に至るまでの状況や判断ミスを確認していきます。そして人間のリスク認知特性を踏まえた上で, どのような対策を講じることが出来るのか, 一緒に考えていきたいと思います。これから起こるかもしれない様々なリスクに適切に対応できるヒントになれば幸甚です。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第10回フォーラム参加希望」として11月29日(水)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 萩元 (TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp
後 援:足立区

日 時:2017年9月2日(土)15時~17時30分
会 場:東京未来大学B棟
主 催:産業・組織心理学会
共 催:東京未来大学モチベーション研究所
≫ポスターはこちらから
モチベーション研究所第9回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「働くひとのメンタルヘルスを支援する―個人, 組織双方へのアプローチ―」
講 師:大庭 さよ(おおば さよ)氏 (医療法人社団 弘冨会 神田東クリニック/MPSセンター センター長)
日 時:2017年 2月25日(土)15時~17時 (受付14時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール (公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
2014年6月の改正労働安全衛生法により50人以上の事業場において義務化されたストレスチェック制度は, 個々の労働者のセルフケア促進と労働者を取り巻く職場の環境改善, いわゆる一次予防を目的としています。
そして, ストレスチェック義務化により企業のメンタルヘルス支援に注目が集まり, 「有効なメンタルヘルス支援とは何か」が改めて問われています。
「有効なメンタルヘルス支援」を実現するためには, 個人, 組織双方に働きかけることが肝要となります。
メンタルヘルス支援において個人, 組織へのアプローチがどのように行われるのか, 実践例を紹介しながら, 働くひとのメンタルヘルス支援のポイントと課題を考えていきます。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第9回フォーラム参加希望」として2月2日(水)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当(TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp
後 援:足立区

モチベーション研究所第8回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「学ぶ意欲をどう高めるか-授業方法と学習方略の視点から-」
講 師:市川 伸一氏 (東京大学大学院教育学研究科教育心理学コース教授)
日 時:2016年10月29日(土)14時~16時 (受付13時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール (公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
学習に対する動機や目的感を6つに分類し, 2次元的に整理した「学習動機の2要因モデル」(市川, 1995)からは, 授業方法の改善がいろいろと示唆される。
一方では, 全員参加型のアクティブ・ラーニングによって, 主体的・能動的な学びを引き出すことが重要である。また, 他方では, 自分の知的向上を実感できるような内容・方法上の工夫も求められる。
とくに, 今回の講演では学習方略の獲得に焦点をあてて, 「このように勉強すれば, 自分もできるようになる」という意欲を引き出すための指導を, 個別学習相談(認知カウンセリング)や授業の具体例をまじえて紹介していきたい。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第8回フォーラム参加希望」として10月26日(水)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当(TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp

モチベーション研究所第7回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「恋愛と結婚における幸せ(Well-being)」
講 師:川名 好裕氏 (立正大学心理学部教授)
日 時:2016年2月6日(土)15時~17時(受付:14時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール (公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
恋人関係や結婚関係においての幸せ(Well-being)とは, どういうことなのでしょうか?日本全国の20代~40代の男女それぞれ1000人にインターネット調査をして男女関係の問題を研究した成果をご報告したいと思います。男女関係は, 友人, 片思い, 恋人, 婚約者, 配偶者と段階が進んでいきます。男女のつきあいの内容は, コミュニケーション, 共行動, 身体接触に分類されます。また, 男女を結び付ける心理的な引力には, 親密性, 情熱性, 性欲性, そしてコミットメント(約束)などがあります。さらに男女関係を崩壊させる要因としては, 意見不一致, 浮気, 嫉妬などがあります。本講演では, 男女関係を幸福に導く要因と不幸に追い込む要因などについて統計分析した結果から示唆されることに焦点を絞ってお話ししたいと思います。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第7回フォーラム参加希望」として2月3日(水)までに上記アドレスまでご所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。
事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 郷田 (TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp

モチベーション研究所第6回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「感謝するとwell-beingは高まるのか?」
講 師:相川 充氏 (筑波大学人間系教授)
日 時:2015年11月14日(土)15時~17時(受付:14時30分~)
場 所:東京未来大学みらいホール (公開講座)
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
ポジティブ心理学の興隆をきっかけに,〝感謝〟に心理学的な注目が集まってきました。欧米の研究では,感謝をすればするほどwell-beingが高まるという結果が出ています。ところが,日本人を対象にした研究では,感謝をしても単純にはwell-beingは高まらないのです。なぜでしょうか?そもそも私たちにとって感謝とは何でしょうか?well-beingを高めるために,どのように感謝すればよいのでしょうか?これらの問いについて,ソーシャルスキルの観点も視野に入れながら,皆様とご一緒に考えてみたいと思います。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第6回フォーラム参加希望」として11月11日(水)までに上記アドレスまで所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。
事前申込をされていなくても当日のご参加が可能ですので, 多くの皆様のご来場をお待ちしています。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 郷田 (TEL) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp
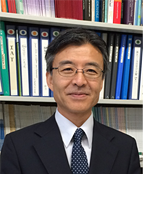
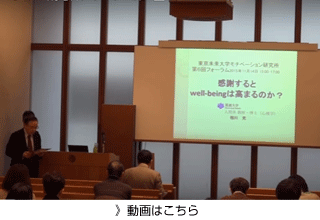
下記, モチベーション研究所の第5回フォーラムは終了いたしました。
題 目:「障害者・高齢者の自己実現を支援する
-well-beingを支える生活機能と生活機能を支える道具(機器)-」
講 師:布川清彦氏 (東京国際大学人間社会学部准教授)
日 時:2015年3月17日(火)15時~17時
場 所:東京未来大学 本館3F 会議室1(公開講座)【注意】東京未来大学みらいホールから変更になりました
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
講演概要:
国内だけでも視覚障害者が約30万人,聴覚障害者が約35万人,肢体不自由者が約170万人,盲聾者約3万人など約300万人の身体障害者がおり,高齢社会の進展とともに中途障害者も増加しつつあります。また,50歳で約25%,75歳で約75%の人たちが何らかの障害を持つともいわれています。障害を持っていても自分らしく生き,自分の能力を十分に試すことができるようにするためには,どうしたら良いのでしょうか。
日本も加盟しているWHO(世界保健機関:人間の健康を基本的人権の一つと捉え,その達成を目的として設立された国際連合の専門機関)は,人間の生活機能と障害を分類するためにICF(国際生活機能分類)という方法を示しました。生活機能とは人間が社会の中で生きていくための機能全体を意味し,障害とは生活機能が低下している状態を意味しています。ICFでは,見ることができないことや足を動かすことができないといった身体や心の働きに問題が生じた状態だけを障害とするのではなく,ある心と身体の有り様を持った人とその人が生活する環境との関係から生活に必要な行為が上手くできなかったり,会社や学校,家庭などで他者と関わる事が難しかったりすることも障害となります。このモデルに従えば,その人に合う環境を整えることで生活機能を向上させることを工夫できるわけです。一方,いくらその人の心身状態に合わせて環境を整えても,その人自身が何か自分でしたいことを持っていなければ,結局は何もしない事になります。そして,何もしないでいる(生活不活発)と心身機能が低下してしまいます。
このフォーラムでは,ICFに基づく新しい障害観とwell-beingを支える生活機能の例として視覚障害者が利用する白杖開発を紹介します。その上で,自分から何かをしたいという意欲の重要性について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
申込方法:Emailにて事前予約制
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第5回フォーラム参加希望」として3月10日(火)までに上記アドレスまで所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数を明記の上, お申し込み下さい。
主催・問い合わせ先:東京未来大学 モチベーション研究所
フォーラム担当 郷田/萩元 (TEL ) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
imsar@tokyomirai.jp
ご案内:本学には, 通常エレベーターとキャンパス内一部スロープ以外に, 障害をお持ちの方に対応できる設備がまだ整備されておりません。この点ご承知おきください。
演者紹介:布川 清彦(ぬのかわ きよひこ)
1998年常磐大学大学院人間科学研究科博士課程修了。東京大学先端科学技術研究センター特任助手,東京国際大学人間社会学部講師を経て,2010年同大学同学部准教授,現在に至る。独立行政法人産業技術総合研究所客員研究員。電子情報通信学会福祉情報工学研究会副委員長。主に,間接的触覚や道具の身体化の解明,支援機器の評価システム構築に関する研究に従事。ヒューマンインタフェース学会,IEEE,電子情報通信学会,日本心理学会,日本特殊教育学会会員。
主要著書・論文:
『福祉技術ハンドブック ―健康な暮らしを支えるために―』(共著 2013), 『Judging hardness of an object from the sounds of tapping created by a white cane』(共著 2014), 『白杖で対象を叩いた時に生じる音を用いた対象の硬さ判断における周波数分析の試み』(共著 2014), 『Vibration of the white cane causing a hardness sense of an object』(共著 2013), 『白杖を用いた対象のテクスチャー知覚-単独歩行する視覚障害者とアイマスクをした晴眼者の比較-』(共著 2013), その他多数。
第4回フォーラムは終了いたしました。
題 目:動機づけの正体-主に感情の役割に注目して-
講 師:速水敏彦教授 (中部大学人文学部心理学科教授・名古屋大学名誉教授)
日 時:10月18日(土)15時~17時
場 所:東京未来大学みらいホール
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
申込方法:予約制 予約〆切10月16日(木)
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第4回フォーラム参加希望」として10月16日(水)
までに上記アドレスまでお申し込み下さい。
(所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数をお知らせください。)
主 催:東京未来大学 モチベーション研究所
問合先:東京未来大学 モチベーション研究所フォーラム担当 郷田/萩元
(TEL ) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
速水 敏彦氏
昭和22年生. 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授を経て, 現在中部大学人文学部心理学科教授・名古屋大学名誉教授。この間, 名古屋大学育学部附属中・高等学校長(2年間), 名古屋大学教育発達科学研究科長(2年間)を勤める。教育学博士(名古屋大学)。
主要著書に, 「コンピテンス―個人の発達とよりよい社会形成のために―」(ナカニシヤ出版, 2012(監修)), 「感情的動機づけ理論の展開―やる気の素顔―」(ナカニシヤ出版, 2012), 「仮想的有能感の心理学―他人を見下す若者を検証する―」(北大路書房, 2012), 「社会的動機づけの心理学―他者を裁く心と道徳的感情―」(北大路書房, 2007(共監訳)), 「他人を見下す若者たち」(講談社現代新書, 2006)など。学術論文多数。
講演概要:
「動機づけ」や「モチベーション」の本当の姿は一体何なのでしょうか。認知が重視される昨今の動機づけ理論の流れに抗って, 感情の役割に注目して学習意欲, 他者軽視, 家事など, 様々な動機づけのメカニズムやその社会的意味について, 皆さんとともに考えてみたいと思います。
第3回フォーラムは終了いたしました。
※今回は, このご案内をお送りした機関ならびに関係者を対象としており, 一般公開はいたしません。
題 目:災害における「喪失」と「社会」~ill-beingからwell-beingへ~
講 師:安藤清志氏(東洋大学社会学部社会心理学科教授)
日 時:2014年2月22日(土)15時~17時
場 所:本館3階の第1会議室
※当初予定していたみらいホールから変更になりました。
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄り駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分,
京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
参加費:無料
申込方法:予約制 予約〆切2月19日(水)
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第3回フォーラム参加希望」として,
2月19日(水)までに上記アドレスまでお申し込み下さい。
(所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数をお知らせください。)
予約制とさせて頂いておりますが, 当日のご参加も可能です。
多くの皆様のお越しをお待ちしています。
主 催:東京未来大学 モチベーション研究所
問合先:東京未来大学 モチベーション研究所フォーラム担当 郷田/萩元
(TEL ) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00)
「Well-beingをめざし明日へのモチベーションを育むために」
第2回フォーラムは終了いたしました。
日 時:10月12日(土)15時~17時
会 場:東京未来大学みらいホール
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分, 京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
講 師:西田公昭教授 (立正大学心理学部・同大学院心理学研究科教授)
講演題目:カルトとマインド・コントロール -well-beingを阻害するもの-
参加費:無料
申込方法:予約制 予約〆切10月9日(水)
Email: imsar@tokyomirai.jp
フォーラム参加をご希望の方は, 「第2回フォーラム参加希望」として10月9日までに
上記アドレスまでお申し込み下さい。
(所属名, 氏名, 連絡先, 参加人数をお知らせください。)
主 催:東京未来大学 モチベーション研究所
問合先:東京未来大学 モチベーション研究所フォーラム担当 郷田/萩元
(TEL ) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM5:00 )

西田公昭(にしだきみあき)氏
関西大学大学院修了(博士)。静岡県立大学准教授を経て, 現在立正大学心理学部・同大学院心理学研究科教授。1994-1995米国スタンフォード大学心理学部客員研究員。日本グループ・ダイナミックス学会常任理事, 日本社会心理学会機関紙編集委員, 実験社会心理学研究編集委員などを歴任。
マインド・コントロールに関する研究の第一人者として, オウム事件などでマインド・コントロール鑑定ならびに専門家証言のために法廷に召喚されること多数。また, マインド・コントロールや詐欺, 悪質商法についての多数のマスメディア出演をはじめ, 消費者庁, 司法研修所, 全国各地の行政機関主催の講演・シンポジウム講師などを務めている。現在, 日本脱カルト協会代表理事, NPO法人小諸いずみ会理事。
主著に『だましの手口:知らないと損する心の法則』(PHP新書 2009), 『まさか自分が・・・そんな人ほどだまされる』(日本文芸社 2005), 『 「信じるこころ」の科学:マインド・コントロールとビリーフ・システムの社会心理学』(サイエンス社 1998), 『マインド・コントロールとは何か』(紀伊國屋書店 1995)など。日本社会心理学会研究優秀賞(「オウム真理教の犯罪行動についての社会心理学的研究」2000年)など学会研究受賞歴多数。
講演概要:
オウム真理教事件の最後の逃亡犯が逮捕されもうすぐ裁判がはじまります。最近の逮捕者は17年経た今でも教祖を崇拝しているという報道がなされ, マインド・コントロールとはそんなに強いものかと不思議に思われている方も多くおられるのかもしれません。私は, 地下鉄サリン事件や坂本事件など数多くの法廷において, ただ一人の心理学者の証人として関わってきました。そして, 今なお繰り返し起きているWellbeingを阻害するマインド・コントロール現象を深く見つめ, 破壊的なカルトや詐欺・悪質商法の被害対策を行っています。このフォーラムでは, オウム事件を知らない若者が増えてきた現代社会で, 我々はこの現象にどう向き合っていくべきかを皆様と一緒に考えたいと思います。
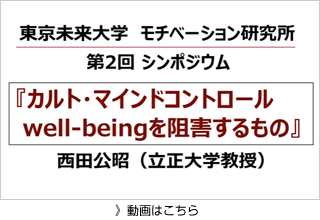
「モチベーションはポジティブな人生を築く」
日 時:2013年5月25日(土)13時~16時30分
会 場:東京未来大学B棟422教室
主 催:日本社会心理学会
協 力:モチベーション研究所
≫ポスターはこちらから
日本社会心理学会第57回公開シンポジウムは, 100名を超えるご参加をいただき無事終了いたしました。
次回も多くの方のご参加をお待ちいたします。
モチベーション研究所フォーラム第1回人はなぜ働くのか
―働くことの中でのwell-beingと仕事への動機づけ―
東京未来大学モチベーション研究所は, モチベーションに関する調査・研究を推進し, 社会的な要請に応えるとともに, モチベーションに関する教育・研究の充実をはかることを目的に開設された, 大学附設の研究機関です。今回, 「人はなぜ働くのか」をテーマに, 下記の通り第1回モチベーション研究所フォーラムを開催いたします。
日 時:1月26日(土)15時~17時
場 所:東京未来大学みらいホール
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
最寄駅:東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「堀切」駅より徒歩2分, 京成本線「京成関屋」駅より徒歩8分
講 師:小野公一氏(亜細亜大学経営学部教授 産業・組織心理学会会長)
参加費:無料
定 員:100名
概 要
近年の働く人々のニーズは, 不況の長期化の中で, 最低限の生活保障すら危うい非正社員や, 長時間労働や子育ての中でワーク・ライフ・バランスを目指す人々, 社会の中での活躍と居場所の確認を重視する人々, そして, 自己の成長・自己実現を目指す人々など, それまでの自己実現的なニーズの中での多様化とは様変わりした多様化を示している。
働く人々のwell-beingはそれらのニーズの充足を通して得られるので, その充足に向けて, 人々は動機づけられることになる。そこでは, ニーズに対応した多様な刺激・誘因についての論議が必要になるであろう。
その一方で, well-beingの充足は何をもたらすのかについての論議も必要になり, 生理的な健康の維持だけでなく, 社会的関係の快適さや, 自己の肯定的評価, 心理的な安寧, そして, 生きがいなどが, 俎上に上がるものと思われる。結果的には, それらを提供できる組織こそが, 働く人々の職務満足感・生活満足感を高め, 組織へのコミットメントを増し, 仕事への自我関与を高め, 課題達成への動機づけを円滑に行いうるものと考えられる。
講師プロフィール
小野公一(おのこういち)
1951年静岡県生/亜細亜大学経営学部教授/亜細亜大学大学院/経営学研究科博士後期課程単位取得退学/株式会社 社会調査研究所(現:インテージ), 亜細亜大学経営学部専任講師・助教授を経て現職/現在, 産業・組織心理学会 会長
<単著>
1.『働く人々のwell-beingと人的資源管理』白桃書房 2011
2.『働く人々のキャリア発達と生きがい』ゆまに書房 2010
3.『キャリア発達におけるメンターの役割』白桃書房 2003
4.『"ひと"の視点から見た人事管理』白桃書房 1997
5.『職務満足感と生活満足感』白桃書房 1993
<共著>
1.『「働く女性」のライフイベント』ゆまに書房 2007
(馬場房子と共著)
2.『産業・組織心理学』白桃書房 2005 (岡村一成と共編著) など
主 催:東京未来大学 モチベーション研究所
問合先:東京未来大学 ( TEL ) 03-5813-2525 (平日AM9:00~PM6:00)
小野公一亜細亜大学教授をお迎えしての第1回フォーラムは, 遠路からお越し下さった方, 近隣の方など, 学内外から40名を超える参加をいただき, 盛況のうちに終了しました。
活発な質疑応答も行われましたが, スケジュールの都合で十分な時間がとれず, まだ質問を残しておられた方にはお詫びいたします。次回も多くの方のご参加をお待ちいたします。
お問い合わせはこちらまで
03-5813-2525
imsar@tokyomirai.jp